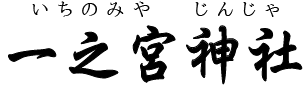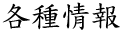天智天皇の御代(668-672)、天皇と大宮姫との間に生まれた一之姫宮が、大宮姫の出生の地であった枚聞神社の御分霊を飛地境内地となっている涙橋の畔(鹿児島市南郡元町)に奉祀したのが創建です。その後、現在地に移転されたと伝えられています。
江戸時代に島津藩で編纂された「三国名勝図絵」に「建久八年(1197)、六月薩摩国図田帳、郡元社、七町五段、鹿児島郡内と戴す」とあり、この郡元社が当社と見られています。
当初より一之宮大明神と称せられ、神領は72町歩(現在の郡元・鴨池・武・田上の一帯)におよび、広大な荘園を抱え、別当寺として延命院をもつ、薩摩国有数の大社となりました。
島津氏の初代当主の島津忠久公以来、毎年元旦には、当社の一之宮、次に二之宮(鹿児島神社)、次に三之宮(川上天満宮)を巡拝する「鹿児島三社参り」が慣いとされ、島津家久の代まで「鹿児島三社参り」は続きました。
元禄期(1688-1704)に神社名を一條宮と改称。明治以前に焼失したものの、現在の中郡小学校の地に建てられていた別当寺の延命院と共に、島津氏、及び近郷の崇敬篤く、隆盛を極めました。明治初期の地租改正の折、郡元神社と改称。昭和30年(1955)に当初の一之宮神社に復しました。
境内には、大永5年(1525年)に道忠との人物が建てた別当寺延命院の遺物と考えられ、昭和34年6月10日に県指定有形文化財に指定された「大永の名号板碑」と、昭和28年9月7日に県指定史跡とされた「弥生式住居跡・一宮遺跡」があります。
1月3日には、打植祭とも三日祭とも称されるお田植神事が斎行されます。その年の五穀豊穣を願って、永年奉仕されているお田植神事で、苗(松葉を代用)、モミ米、重ね餅を供えて祈願祭を行い、続いて木製の牛を引いて社殿を三周し、社前に設けられた斎田で農耕の諸所作を行い、宮司がモミ米を散布して神事が終了します。尚、牛を撫でさすった餅を食すればその年は無病息災とされています。