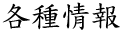釜蓋神社とも称される射楯兵主神社の創建は不詳ですが、枚聞神社の末社として平安時代の中期には創建されていたと伝えられています。御祭神は素戔嗚命で、高さ30cmの石体が御神体となっています。
開聞岳の周辺には、開聞岳の麓で生まれ、宮中に入るも戻ってきた大宮姫、そしてそれを追ってきた天智天皇の御巡幸伝説が残されています。天智天皇と大宮姫は、頴娃村の御領に住んでいた安東実重中将を尋ねます。中将が、その接待のため何十石という米を蒸しているとき突風が吹き、釜蓋が吹き飛ばされてしまいます。飛んで行った釜蓋は、当地(大川浦)に落ち、土地の人々が、この釜蓋を拾い神として祀り、竃蓋大明神と名付けて奉ったとされています。その後、素戔嗚命を配祀したと伝えられています。
寛文7年(1667)の第2代薩摩藩主・島津光久による「頴娃郷神仏誌」にたびたび修復のことが記されています。享保元年(1716)8月15日炎上しますが、翌享保2年(1717)11月25日再建され、その時の棟札に「開聞宮末社釜蓋大明神」と記されています。天保14年(1843)6月の吉日に、第10代薩摩藩主の島津斉興が国家鎮護・武運長久の祈願をされています。
戦時中は武の神様として仰がれ、釜蓋をかぶって参拝すると、無事に帰ってこられるということで、多数の参拝客が訪れました。現在も「かまふた願掛けかぶり」として伝えられており、備え付けの釜蓋を頭の上に乗せ、手を使わずに鳥居から賽銭箱前までお参りすると武道、勝負、厄除け、開運の御神徳があるとされています。
社殿の向かって右手には、寿石が祀られており、石を撫でながら祈願すると良縁、子宝、安産の御神徳があるとされています。
](img/logo-title.png)