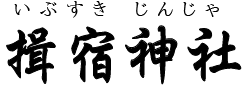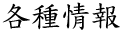社記によれば、揖宿神社は、天智天皇が薩摩地方を御臨幸の折り、当地に御滞興あらされた由緒の地として、慶雲3年(706)2月10日に賀茂縣主堀内氏、指宿氏の遠祖が勅を奉じて、天皇の神霊、遺器を奉斎して葛城宮がご創建されたのが創始です。貞観16年(874)7月の開聞岳の噴火の際、開聞十町に鎮座する枚聞神社(開聞九社大明神)が葛城宮に御避難されたいとの御神託により、同年11月に枚聞神社は当地に遷座します。噴火が終息して枚聞神社は、お戻りになりますが、以来、当杜を「開聞新宮九社大明神」として奉斎し、指宿の総氏神「お新宮様」の称号で親しまれるようになります。地方開拓の祖神、航海安全、諸業繁栄、交通航海安全の守護神として崇敬せられ、殊に代々薩摩藩主の尊崇厚く、沿革記によると32度に及ぶ社殿の改修等全て藩費をもって施行されたとあります。明治維新に際し「揖宿神社」と改称され、郷社に列せられました。
現在の社殿は、弘化4年(1847)12月18日時の第27代薩摩藩主の島津斎興により改築されたもので、入母屋造の本殿を始め勅使殿・摂社に至る迄、全てに楠材が使用されています。本殿・弊殿・舞殿・拝殿・勅使殿が連結して 一体の建造物となっており、舞殿126枚に、勅使殿の格天井には64枚の荘厳な花木絵が描かれ参拝者の心を和ませてくれています。
往時は木造の鳥居でしたが、社殿御造営の翌年の嘉永元年(1848)に造られた鳥居が現在の石鳥居です。肥後の名石工・岩永三五郎の作で、石材は御影石。大隅半島の大根占から舟で搬送されました。陸上げの際、鳥居最上段の笠木を海中に落とし、どうしても陸上げできず、再度大根占より搬送し建立されました。その時、揖宿神社の神様が「牛を嫌う」という言い伝えにより、車に積んで多くの人々による人力で海岸から神社まで運んだといわれています。尚、鳥居建立と社殿御造営の費用は同額を要せりと記録にあります。
境内には摂末社が多く鎮座しています。鳥居を過ぎての随神門には、経津主命と武甕槌命が祀られ、境内の守りを固めています。随神門の向かって右脇は、当社の社家であった賀茂縣主堀内氏、指宿氏の祖神とされる大山積命を祀る山之宮です。
社殿向かって右、本殿側から玉依姫命を祀る天井宮と豊玉姫命を祀る姉姫宮がひとつの社に鎮斎されています。そして天命開別命(天智天皇)を祀る西之宮。その手前が大己貴命を祀る荒仁宮です。
社殿向かって左、本殿側から昭美日月命を祀る懐殿宮と塩土翁命を祀る聖宮がひとつの社に鎮斎されています。そして和田都美命を祀る二龍宮、彦火火出見命(山幸彦)を祀る東之宮が鎮座しています。
境内には、推定樹齢700年以上のクスノキの大樹が8株も群生し、その周りには、エノキやイチョウなど、高さが20mを超える大木がまとまって生え、大木にはアコウの木が寄宿し木根を長く垂らしているなど、県内でも珍しい社叢とされています。能面や神輿など数多くの宝物が伝えられており、特に室町時代中期の作とされている尉面(男の老人の顔)、姫面(若い女性の顔)、狂言面の三面は、日本で能や狂言が完成されたころの貴重なもので、社叢と能面は、共に県指定文化財に指定されています。
揖宿神社の石鳥居の前には、ムクノキがあります。このムクノキは、「田の神」が樹木に宿ると伝えられている珍しい事例で、「田の神」の石像が作られる前の信仰のかたちを伝えるものとされています。揖宿神社では、昭和28年頃まで、このムクノキの下でお田植え祭りが行われていました。ムクノキの裏側には、大正8年(1919)に造られた「田の神」も祀られています。
旧暦3月20日は、天文14年(1545)から続く伝統行事である揖宿神社の浜下りの日です。祭典の後、高さ4mの猿田彦命の人形山車を先頭に、2時間余りかけて神幸行列が斎行されます。2年に1度、宮ヶ浜地区と湊地区で交互に行っており、この行列にお供した稚児は、健康で素直な子に育つとされています。
また、文政11年(1828)に薩摩藩の財政改革主任に大抜擢された調所笑左衛門広郷が、弘化4年(1847)11月10日に寄進した手水鉢も見所です。
当時の薩摩藩の年間予算は12~14万両で、借金の総額は500万両。その利息の支払いだけで年間80万両を超えていました。調所笑左衛門広郷は、黒砂糖などの国産品の販売、唐物の密貿易、その交易の優先権の代わりに借金を無利子の250年分割支払いにし、踏み倒しするなどして、劇的な財政再建を果たします。それだけに藩にとって海運業の育成は不可欠なもので、その調所の政策を支えたのが、濵崎太平次や河野覚兵衛ら指宿の海商たちとされています。