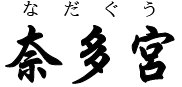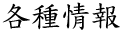奈多宮の鎮座地は、比売大神発祥の霊地であるとともに、八幡神(応神天皇)が顕現する前に遊幸した地です。創建は不詳ですが、社殿として創建されたのは、宇佐宮が現在の小椋山に創建された神亀2年(725)の4年後の天平元年(729)、聖武天皇の叡聞に達し、宇佐公基に勅して創建されたと伝えられています。御祭神として[第一神座] 比売大神、[第二神座] 応神天皇、[第三神座] 神功皇后を祀っています。

奈多海岸の沖合約300mには、元宮とされる市杵島の岩礁の上に小鳥居が建てられており、古くから比売大神を祀り、守護神として尊崇してきたとされています。比売大神は、素戔鳴尊と天照大神の誓約により素戔鳴尊から生まれた瀛津嶋姫命(市杵嶋姫命)、湍津姫命、田霧姫命の三女神とされ、その降臨した宇佐嶋が市杵島とされています。
『日本書記』卷第一 第六段一書第三
一書曰、日神與素戔鳴尊、隔天安河、而相對乃立誓約曰、汝若不有奸賊之心者、汝所生子、必男矣。如生男者、豫以爲子、而令治天原也。於是、日神先食其十握劒化生兒、瀛津嶋姫命。亦名市杵嶋姫命。又食九握劒化生兒、湍津姫命。又食八握劒化生兒、田霧姫命。…(略)…。其素戔鳴尊所生之兒、皆已男矣。故日神方知素戔鳴尊、元有赤心、便取其六男、以爲日神之子、使治天原。卽以日神所生三女神者、使降居于葦原中國之宇佐嶋矣。今在海北道中。號曰道主貴。此筑紫水沼君等祭神是也。熯、干也。此云備。
一書に曰く、日神、素戔鳴尊と、天安河を隔てて、相対ひて乃ち立ちて誓約ひて曰はく「汝若し奸賊ふ心有らざるものならば、汝が生めらむ子、必ず男ならむ。如し男を生まば、予以て子として、天原を治しめむ」とのたまふ。是に、日神、先づ其の十握劒を食して化生れます児、瀛津嶋姫命。亦の名は市杵嶋姫命。又九握劒を食して化生れます児、湍津姫命。又八握劒を食して化生れます児、田霧姫命。…(略)…。其れ素戔鳴尊の生める児、皆已に男なり。故、日神、方に素戔鳴尊の、元より赤き心有ることを知しめして、便ち其の六の男を取りて、日神の子として、天原を治しむ。即ち日神の生れませる三の女神を以ては、葦原中国の宇佐嶋に降り居さしむ。今、海の北の道の中に在す。号けて道主貴し曰す。此れ筑紫の水沼君等が祭る神、是れなり。熯は、干なり。此をば備と云ふ。
また、『八幡宇佐宮御託宣集』では、比咩大神として示現する以前は、神武天皇の母神である玉依比咩命として、当地の国加郡(国東郡)に住んでいたとも伝えています。
『八幡宇佐宮御託宣集』国巻四・三所宝殿以下事
二御殿。食封二千戸。
人皇第一神武天皇御母玉依姫之御霊也。聖武天皇御宇天平年中。有託宣有。示現比咩大御神前。住国加郡玉依比咩命也。
二御殿。食封二千戸。
人皇第一神武天皇の御母、玉依姫の御霊なり。聖武天皇の御宇天平年中、託宣有り。比咩大御神の前に示現し、国加郡に住みたまふ玉依比咩命なり。
天平神護元年(765)10月8日の神託では、八幡大神(応神天皇)が対岸の宇和島からの遊化したことを伝えています。奈多の浜辺の海中には大きな石があり、八幡神はそこで気を安め御机石と名付けます。その石が、市杵島と考えられています。その後、松本(見立山)にのぼり、辺りを見渡して御立野と名付け、後に秋庄と称される安岐の林に至ったと伝えています。
『八幡宇佐宮御託宣集』威巻七・大尾社部(下)
一。称徳天皇元年。天平神護元年乙巳十月八日。従三位大弐臣石河豊成賷勅書向大神宮。託宣有其員。其次事別而宣。
吾昔伊興国宇和郡往来時。豊後国々崎郡安岐郷奈多浜辺海中有大石。其渡吾渡着。気安号御机石。即奈多松本登有。其上野登可住所々案内見。其野号御立野。自其至安岐林。後号秋庄。
一。称徳天皇元年、天平神護元年乙巳十月八日、従三位大弐臣石河豊成、勅書を賷つて大神宮に向ふ。託宣其の員有り。其の次の事別に宣く。
吾昔伊興国宇和郡より往来の時、豊後国々崎郡、安岐郷奈多の浜の辺の海の中に、大石有り。其の渡に吾渡り着きて、気を安め、御机石と号す。即ち奈多の松の本に登つて有りき。其の上の野に登つて、住む所々の案内を見き。其の野を御立野と号す。其より安岐の林に至る。後に秋庄と号す。
社殿として創建されたのは、宇佐宮が現在の小椋山に創建された神亀2年(725)の4年後、天平元年(729)宇佐公基により創建されたと伝えられています。以降、奈多宮では宇佐公基を先祖とし、代々奈多氏が宮司を務めます。奈多宮は当初から宇佐宮との関りが深かったとされますが、行幸会を通じてより深い繋がりを持つようになります。
隼人制圧の際、八幡神の御験とされた薦枕は、それ以降も八幡神の御験として用いられます。その八幡神の御験の薦枕造替にかかわる一連の神事が、宇佐宮の行幸会です。薦枕は、6年毎に薦神社の三角池のマコモを刈って、新しく造り替えられます。三つの御殿の御神体をそれぞれ神輿にお乗せして、八幡神が顕現する前に巡行した八つの神社(田笛社・鷹居社・郡瀬社・泉社・乙咩社・大根川社・妻垣社・小山田社)を廻った後、宇佐宮本殿に納める宇佐宮最大の神事でした。古い御験は下宮に、さらに下宮の古い御験は、国東半島東海岸の奈多宮に納められ、最終的には海に流されました。天平神護元年(765)10月8日の神託では4年に1度、行幸会を斎行することを宣っています。
- 薦神社で八幡神の御神体である薦枕の材料の真薦を苅る。
- 宇佐宮下宮に戻り、鵜羽屋を造る。
- 鵜羽屋に大神氏の神官が17日間参籠し、一心に気を収めて、薦枕をつくる。
- 宇佐宮上宮の各神殿に新しい御神体を奉る。
- 宇佐宮上宮の旧御神体を下宮に遷す。
- 宇佐宮下宮の旧御神体を奉り、宇佐の八ヶ所の別宮を巡幸する。
- 奈多宮に宇佐宮下宮の旧御神体を奉る。
- 奈多宮の旧御神体を海に流す。
弘仁2年(811)以降、行幸会は卯と酉の年、6年に1度に改められました。『八幡宇佐宮御託宣集』に行幸会の詳細が記されています。
『八幡宇佐宮御託宣集』威巻七・大尾社部(下)
神服。神宝等者。六年一度雖公家貢進矣。今就神託依府符。御行之御出立奉調進神服等。令荘厳斎殿。奉裏荘御験也。相当卯酉之年。七月初午之日。御装束所忽検校。祝。権祝。陰陽師並神人等。自菱形宮参薦御池。御杖人奉苅調之。御輿持奉荷捧之。任先例令警蹕帰本宮。下宮着。神官松本着座礼節。御薦案上暫在。而有御祓。奉入当社神前。奉安申殿梁上。神服以下被調之後。令造鵜羽屋。大神氏神官一七日参籠一心収気奉裏成之。御長径御錦等巳神慮之趣如被定之文。旧御験者奉安下宮。下宮御験者奉乗旧神輿。奉渡奈多宮而巳。新御験者自鵜羽屋有御出。神官勢々警蹕。経正道而入奉正殿。旧御験者自西妻戸有御出。神官少々無音廻閑道而入御下宮。下宮御験又奉遷奈多宮。是即以御影移行。被示世間転変也。
神服・神宝等は、六年に一度、公家貢進したまふと雖も、今神託に就き、府の符に依つて、御行の御出立として、神服等を調進し奉り、斎殿を荘厳せしめ、御験を裏み荘り奉るなり。卯酉の年七月初午の日に相当り、御装束所の忽検校・祝・権祝・陰陽師並に神人等、菱形宮より薦御池に参り、御杖人これを苅り調へ奉り、御輿持、これを荷ひ捧げ奉る。先例に任せて、警蹕せしめて本宮に帰り、下宮に着く。神官、松の本に着座して、礼節有り。御薦案上に暫在り。而に御祓有り、当社の神前に入り奉り、殿の梁の上に安き申し奉る。神服以下調へらるる後、鵜羽屋を造らしむ。大神氏の神官一七日参籠し、一心に気を収めて、これを裏み成し奉る。御長径御錦等は、巳に神慮の趣、定めらるる文の如し。旧き御験は、下宮に安き奉り、下宮の御験は、旧き神輿に乗せ奉り、奈多宮に渡し奉るのみ。新しき御験は、鵜羽屋より御出あり。神官勢々警蹕して、正道を経て、正殿に入れ奉る。旧き御験は、西の妻戸より御出有り、神官少々音無しに、閑道を廻つて、下宮に入れたまふ。下宮の御験は、又奈多宮に遷し奉る。是れ即ち御影の移り行くを以て、世間の転変を示さるるなり。
永延2年(988)には、「この宮は初中後(過去・現在・未来)にわたって最上の八幡である」と一条天皇の叡感に預かり、「日本斎場八幡初中後廟」の額を、大宮司奈多国基に賜わるなど代々朝廷の御尊崇は極めて篤いものがありました。関白の藤原道長(966-1028)は、「一宮海雲楼」、「三韓降伏」の額を楼門に揚げたとされ、康和年中(1099-1103)には承徳2年(1098 )に大宰権帥として太宰府へ着任していた大江匡房が「一楼台」の額を奉納したと伝えられています。朝廷からの尊崇も篤く、行幸会は、後花園天皇(1428-1464)まで奉じられますが、戦国となって中断します。
代々宮司を務めていた奈多氏は、当地方に巨大な勢力を持ち、大友氏の武将としても活躍します。戦国時代には、宇佐宮と激しく対立し、 永禄4年(1561)には宇佐宮を焼き討ちしていたキリシタン大名の大友宗麟が、奈多大宮司の奈多鑑基の娘を正室として娶り、奈多氏は栄華を極めます。しかし、奈多鎮基が天正15年(1587)に没後、家督を継ぐ者がないため豊臣秀吉から神領を没収され、奈多氏は断絶します。さらに文禄5年(1596)慶長豊後地震の津波により、一条天皇宸筆の額をはじめ、神殿・拝殿・楼門・鳥居などの古記録を悉く流失しました。
慶長4年(1599)から細川忠興が当地の領主となり、慶長5年(1600)には豊前国と豊後2郡(国東・速見)も治めるようになります。細川忠興は、宇佐宮、薦神社、奈多宮等の寺社の復興に努め、奈多宮の再建費用として白銀三十六貫目を寄進。元和2年(1616)には、行幸会を復興し、行幸会の当時は仮宮でした。寛永4年(1627)9月10日、杵築城城代の長岡興長(当時は松井興長)により、流失した建造物の根本的な造営が完成。再建に際し、残った社銀を受け取らなかった長岡興長にお伺いが立てられ、寛永19年(1642年)長岡興長の銘により楼門・鳥居・手水鉢などが建立されました。
宝物殿に現存する額は寛文3年(1663) 細川忠興の六男で長岡興長の養嗣子であった長岡寄之が奈多宮に参拝して奉納したもので、松堂隠元の筆です。細川氏、その後を継いだ小笠原氏、松平氏の各藩主共に崇敬怠らず、神田造営などの寄献、補修が行われました。明治6年(1873)2月20日に県社に列格。明治14年(1881)本殿以下拝殿、廻廊などを改営しました。尚、行幸会は元和2年(1616)を最後に途絶しています。
拝殿の奥の正面が本殿。向かって右手の社が、若宮、若姫、宇礼、久礼を祀る若宮殿。向かって左手は、産霊神、菅原道真公を祀る北辰社です。尚、北辰社は宇佐神宮で比咩大神を祀る第二神殿の脇社でもあります。
本殿は八幡造りで「八幡造」は、宇佐神宮、柞原八幡宮(大分市)、奈多宮(杵築市)、大帯八幡宮(姫島村)、石清水八幡宮(京都府)、伊佐爾波神社(愛媛県)など類例のみの独特な建築様式です。切妻造平入の2棟(内院・外院)が前後に並んでいます。奥殿の内院には、御帳台が置かれ、夜の御座(寝室)とされています。前殿の外院には、御倚子が置かれ、昼の御座(居間)とされています。御帳台と御倚子のいずれも御神座とされています。大神は、その内院と外院を昼夜行き来しているとされています。

境内には、宝物殿近くに田道間守公像が祀られています。柑橘の始祖、ミカン・菓子の神様とされる田道間守は、垂仁天皇の御代に勅を奉じ、橘を求めて常世国に渡り、10年以上かけてミカンを持ち帰朝しました。しかし天皇は、既に崩御されており、公は御陵前で哭死されたと伝えられています。像は昭和25年(1950)の造営です。
また、「日本の白砂青松100選」に指定されている奈多海岸は、良質な砂鉄の産地で、境内西の三立山山麓一帯には製鉄遺跡が広がっています。奈多宮の南西方向に古墳時代中期の大きな亀山古墳があり、古くから製鉄の技術を有した強力な豪族がいて、鉄を主体とした文化が栄えていたと考えられています。
【文化財】
「神像三躯」
国指定重要文化財。女神像・伝比咩神(像高49cm)、僧形八幡座像・伝応神天皇(像高53.5cm)、宝冠の女神座像・伝神功皇后(像高55.2cm)の三神像。榧の一本造りで、藤原時代の優れた芸術品で、ふくよかで端正な尊顔、温雅な中に威厳があります。昭和25年8月29日の指定。
「若宮神像」
県指定文化財。若宮の神像として宇礼、呉礼、若比古、若比賣、小若宮(2躰)の6躰。
【神事・祭事】
「田植祭」
毎年4月5日に斎行されます。古くは不明ですが、文政4年(1821)の古文書に由緒を見る祭りで、五穀豊穣を祈る農耕予祝儀礼です。田んぼに見立てた境内で神歌を歌いあげた後、鍬を引いた牛が苗代掻きをすると、柄振り突きが斎田を均し、早乙女の準備を促します。田植神主、太鼓打ち、柄振り突きが並ぶ後に早乙女を演じる6人の男子が整列し、田植え唄を交互に歌いながら田植の所作をします。次に弁当を持ってきた妊婦が産気づき出産し、その弁当持ちを早乙女が榊で叩きながら追う様を演じます。狂言の影響をより強く受けているとされています。平成12年3月24日に県無形文化財に指定されました。