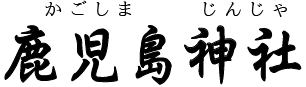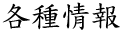鹿児島一円の地主神と伝えられる鹿児島神社は、遠く神代より、鹿児島というこの地の言霊と共に今に来たりました歴史ある古社です。古くは桜島の袴腰台地に鎮座し、鹿児島一円の氏神として、海の神として奉斎されています。
御祭神は彦火火出見命、豊玉姫命、そして豊玉彦命。彦火火出見命は、海幸彦・山幸彦の伝説で知られる山幸彦で、豊玉姫命はその后神です。豊玉彦命は、豊玉姫の父神である海神の大綿津見神の別称とされ、彦火火出見命が綿津見宮に行かれた折、心を尽して仕えたとされています。その誠忠偉勲の功を称える為、彦火火出見命の御子の鵜茅葺不合命が創祀されたと伝えられています。また、現在地の玉里地区はかつての当社の神田であり、そこに祀られていた豊受大神を合祀しています。
創建年代は不詳ですが、延喜元年(901)に記された「日本三代実録」にて、「貞観2年(860)3月20日薩摩國従五位下鹿児島神に従五位上を授く氏神は鹿児島の地主神なり」と記された「鹿児島神」に比定されています。
後、鹿児島神社は桜島の噴火により草牟田に遷座し、現在に至っています。境内に残されている扁額と石鳥居は、その袴腰地区に鎮座していた当時のものと伝えられています。尚、桜島の西南西、錦江湾に浮かぶ小島の神瀬は、飛び地境内で、鹿児島神社の海の里宮、遥拝所であったとされています。
古来、宇治瀬神社とも称され、「宇治瀬様」を薩摩弁で「ウッテサァ」と呼んで親しまれています。宇治瀬とは、錦江湾の瀬のいと早く渦巻く様とも、また、以前は当社下を流れていたという甲突川の早瀬の逆巻く様に由来するとも伝えられています。現在地の草牟田の近くには、入船との地名も残っており、江戸期までは、当地域が船着き場とされていました。
また、春祭の2月18日から秋祭(ホゼ祭)の10月18日までの期間は「宇治瀬」と呼び、それ以降の半年を「宇津佐」と言い分けて呼び慣わしています。また、例祭の執行される2月と10月を「神月」、殊に18日のお祭りを迎えるまでを「柴内」と呼んで、氏子等は其の間、旅行其の他を悉く忌み慎みました。この「神月」が、「甲突」と変化し、甲突川の名の起こりとなった考えられています。
藩政時代には、領主島津家の尊崇厚く、島津氏の氏祖の島津忠久は、正月と家督を相続すると、まず初めに参詣する例とされた鹿児島三社(一之宮神社・鹿児島神社・川上天満宮)の必のひとつとされていました。第18代当主の島津家久(1602-1638)の代で三社詣りは廃絶しますが、天保6年(1835)に、第26代当主の島津斉宣によって建てられた島津家別邸「玉里邸庭園」も当社の近隣であったのが造営の理由であったとされています。
安政2年(1855)には、大火にあった京都御所の安政造営の再建に際し、時の藩主の島津斉彬により御神木の大杉が供出され、それに共に切妻造平入の本殿が起工されます。本殿は、島津斉彬の没後の安政6年(1859)に竣工し、同年に正一位の神階を賜わっています。明治5年(1872年)には県社に列し、現在に至っています。
鳥居を過ぎ、参道の両脇には、豊磐間戸命と櫛磐間戸命を祀る門守神社が鎮座しています。向かって右手の門守神社の奥には、地神・水神を祀る石祠が並びます。手水舎の向かいの石祠は、田之神と蛇神を祀っています。
また、田之神舞、宮毘舞、鬼神舞、剣舞、薙刀舞の5つの神舞が伝えられていて、春と秋の例大祭、夏越祭六月灯にて奉納されています。