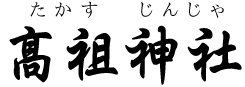高祖山の西麓に鎮座する髙祖神社は、中座に彦火々出見命、左座に玉依比売命、右座に息長足姫命(神功皇后)の三柱をお祀りする神社です。『日本三代実録』の元慶元年(877)の項にて「筑前国正六位高磯比売神に従五位下を授く」と神階の授与が記された国史見在社です。高磯比売神とは髙祖神のことで、相殿に玉依比売命、息長足姫命をお祀りしてあるので、このように呼ばれたと語り伝えられています。
『日本三代実録』卷三十二
元慶元年(877)九月廿五日癸亥。授筑前國…(略)…。正六位上高磯比咩神從五位下。
創建は不詳ですが、社伝では、歴世の天皇は皇祖神とされる彦火々出見命の裔孫であることから髙祖神と称されるようになったと伝えています。また、神功皇后が三韓征伐に向かう時、香椎宮より当地まで御幸があり、髙祖神に三韓征伐がなるように祈りを捧げます。無事に帰還できた神功皇后は、神恩に感謝し、報賽の御祭として新たに御宮を造り、異国降伏ために西面した御社を建てたとされています。そして後世至り神功皇后も祀るようになったと伝えています。孝謙天皇の御代(749-758)に吉備真備に勅して怡土城が築かれ、怡土城鎮護の神とされました。
建久8年(1197)原田種直が怡土城の旧跡を再興して高祖城を築き、城中の鎮護の神として崇敬されます。当時は、現在より約800mの大霜(大下)に鎮座していたとされています。高祖城主・原田氏からの崇敬厚く、毎年正月元日、15日、2月初卯、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日、11月初卯には原田氏が祭主となり祭典が行われ、殊に9月26日の大祭では原田氏の当主が御輿に供奉して御幸したと伝えられています。
永正4年(1507)7月10日に当時の原田興種が現在地へ遷宮。天文10年(1541)12月19日に原田隆種が再興します。この造営時の棟札で当社は、怡土郡一宮と記されています。元亀3年(1572)にも原田親種により修造が行われます。天正14年(1586)豊臣秀吉による九州平定の際、島津氏に服属していた高祖城主の原田信種は、高祖城に立て籠もり豊臣軍に対抗するものの、戦わずに投降して高祖城を退去します。高祖城は破却されることになりますが、髙祖神社は怡土郡の総社として尊崇を受け続けます。
寛文2年(1662)福岡藩主・黒田光之が材木を全て寄附し、修補を加えて再建。現在の本殿は、この時の造営によるもので、三間社流造の檜皮葺です。造営時の姿をそのまま留めていることから、福岡県下でも極めて貴重な建造物として高い評価を得ています。元禄6年(1693)には福岡藩主・黒田綱政から境内入口の石造明神鳥居の寄進。享保16年(1731)には正面三間、側面三間、入母屋造の拝殿が建立されました。
明治5年(1872)11月に怡土郡の郷社の指定。大正4年(1915)1月12日に許可を得て、同月22日に伊勢大神宮を合祀。伊勢大神宮は、永正期(1504-1521)原田氏が大内氏の幕下であった時代、乱世により伊勢神宮へ参宮できなかったことから周防国・山口大神宮を勧請したと伝えられています。原田氏滅亡の後、旧臣の当地に残る氏子により大神宮宮座が組織されています。同年(1915)11月10日に神饌幣帛料供進社の指定。大正15年(1926)6月29日に県社へ昇格。平成24年(2012)3月26日に本殿、拝殿および石鳥居などが福岡県の有形文化財建造物に指定されました。
【境内社など】
「徳満神社」
参道を進んで左脇に鎮座。明治10年(1877)3月に宗像郡・徳満神社の分霊を祀ったのが創始です。牛馬を始め、動物の守護神として崇められています。昔から牛馬の神様として、近年はペットの守り神として崇められています。御祭神は大名持神・少彦名神・保食神です。例祭日9月13日。毎年祭日には宗像本社の祭典に準じ、神酒・御供を参拝者に供し、初穂を献じた者には中飯を出されています。
「伊弉諾神社」
社殿後方向かって右手に鎮座。由緒不詳。御祭神は、伊弉諾大神、伊弉冊大神。
「思兼神社」
社殿後方向かって左手に鎮座。由緒不詳。御祭神は、思兼命、菅原大神。
【神事・祭事】
髙祖神楽
 髙祖神楽・は、応仁元年(1467)高祖城主・原田種親が盟主である周防国山口城主・大内政弘の要請を受けて京都守護の大任に当った時、戦陣のつれづれに習得した「京の能神楽」を郷土に伝えたものとされています。この外にも異説があり、その始めは定かではありません。永い歴史と伝統に受け継がれて来た髙祖神楽は、江戸時代までは旧怡土郡の神職の奉仕で舞われていました。明治になってからは髙祖神社の氏子の人たちによって受け継がれ、現在は十数人の氏子の神楽師の奉仕で、春と秋の年2回、社殿前の神楽殿で奉納されています。春の祈年祭では午後2時頃から夕方まで、秋大祭前夜祭では午後6時頃より10時頃まで、篝火の薄明りの中で斎行されています。現在奉納されているのは、面を着けずに採り物(降神の宿る所になる鈴・剣・玉のこと)を捧げて楽の音にあわせ神楽歌を唱えながら静かに舞う舞神楽と、面を着けた数人の神楽師が登場して神話物語りを展開させてゆく面神楽の2種類11番(神供、高処、笹舞、国平、蟇目、磯羅、敷蒔、神相撲、両剣、御弓、御剣、問答、岩戸開き)、地元の子どもたちにより「両剣神楽」や「稚児舞」なども奉納されています。昭和46年(1971)5月19日には前原町指定民俗文化財、昭和56年(1981)3月5日には福岡県無形民俗文化財の指定を受け、格調高い郷土芸能として評価されています。
髙祖神楽・は、応仁元年(1467)高祖城主・原田種親が盟主である周防国山口城主・大内政弘の要請を受けて京都守護の大任に当った時、戦陣のつれづれに習得した「京の能神楽」を郷土に伝えたものとされています。この外にも異説があり、その始めは定かではありません。永い歴史と伝統に受け継がれて来た髙祖神楽は、江戸時代までは旧怡土郡の神職の奉仕で舞われていました。明治になってからは髙祖神社の氏子の人たちによって受け継がれ、現在は十数人の氏子の神楽師の奉仕で、春と秋の年2回、社殿前の神楽殿で奉納されています。春の祈年祭では午後2時頃から夕方まで、秋大祭前夜祭では午後6時頃より10時頃まで、篝火の薄明りの中で斎行されています。現在奉納されているのは、面を着けずに採り物(降神の宿る所になる鈴・剣・玉のこと)を捧げて楽の音にあわせ神楽歌を唱えながら静かに舞う舞神楽と、面を着けた数人の神楽師が登場して神話物語りを展開させてゆく面神楽の2種類11番(神供、高処、笹舞、国平、蟇目、磯羅、敷蒔、神相撲、両剣、御弓、御剣、問答、岩戸開き)、地元の子どもたちにより「両剣神楽」や「稚児舞」なども奉納されています。昭和46年(1971)5月19日には前原町指定民俗文化財、昭和56年(1981)3月5日には福岡県無形民俗文化財の指定を受け、格調高い郷土芸能として評価されています。